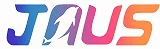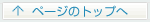日本水中科学協会Japanese Academy of Underwater Sciences
3 トレーニング基準
3.1 トレーニング総則
3.1.1 トレーニングとは
トレーニングはスポーツである。スポーツについて、さまざまな定義がなされているが、簡単に言えば、喜び、楽しみのための身体活動である。研究活動のためのトレーニングであっても、身体を動かすことに喜びを感じ楽しくなければ、継続することはできない。
トレーニングのすべてについて、強制は厳禁であり、自己責任による安全管理で行う。 コーチ及び統括責任者は、各自のトレーニングが限界を超えていないか、健康管理(自己申告)が適正であるかについて監督することが主務である。コーチは、現場での安全管理を行うとともに、フォームの矯正、技術幇助、なども行うが、上達して勝利しなければならない競技選手の監督・コーチとは、性格がまったく異なる。
3.1.2 エントリーレベルトレーニング
トレーニングそのものも、決して絶対の安全が保証されているわけではない。不完全な講習を修了してきた初心者ダイバーの実習がもっとも危険が大きいとも言える。特別に、コーチ及びリーダーが付き添って、一般の講習修了者レベルに到達するまで慎重にトレーニングを行う。
3.1.3 習熟トレーニング
講習で教えられても、その技術に習熟したことにはならない。
教えられたことが出来るようになることを習得、目をつぶっていても出来るように練習を積んだ状態を習熟という。教えられた後、その技術を自分のものにするためのトレーニングを習熟トレーニングという。
3.1.4 技能維持トレーニング
習熟した技術を維持するために日常的に続行するトレーニング。
ダイビングを続ける限り、トレーニングは欠かしてはいけない。
3.1.5.フィットネストレーニング
ダイビングは、身体能力が要求されるので、身体能力を活動に適合させ維持するためのフィットネストレーニングも必要である。
①水泳
②ランニング
③自転車
の三つがフィットネストレーニングの定番であるが、プールが近くにある限り、ダイビングについてのフィットネストレーニングは、水泳を中心にする。
3.2 トレーニング安全基準
3.2.1 監視態勢
①トレーニングは、必ずコーチもしくはトレーニング基準を熟知したリードダイバーが直接管理して行う。
②スキンダイビング・トレーニングは、一人にしてはいけない。必ず、水中に他の目がなければいけない。
バディの他に監視役が一緒に水中に入って見張っていることが望ましい。三人ないしは4人のダイバーが一緒にトレーニングすることを薦める。
③実海域でのスキンダイビングトレーニングは、水面に小舟(ゴムボート、カヤックなど)もしくは、タイヤチューブなどの浮きを置いて行う。
※海女さんは浮樽を浮かべて潜る。
④C-カードを持っていない人、あるいはテストの結果、C-カードのレベルに達していない人に対するトレーニングをエントリートレーニングと呼ぶが、必ずコーチもしくはリードダイバーがマンツーマンで行う。
⑤エントリートレーニングでの浮上は、必ず直接管理でコーチもしくはリードダイバーが受講生に手を伸ばせば届く状態で行う。
⑥急浮上してしまう可能性のあるスクーバダイビング練習を水深1.5m以上で行うことを厳禁する。3.で述べる肺圧外傷予防のためである。
3.2.2 自己責任と強制の禁止
①監視態勢を整えることは、統括責任者およびコーチの責任であるが、その態勢下で起こる事故の責任はすべて、本人にある。
※息を止めて浮上するなと言っても、息を止めるのは本人であり、監視者が息を止めるわけではない。
②統括責任者、およびコーチは、決して強制してはいけない。強制を匂わしてもいけない。※「これがうまくできれば、認定が修了するから、がんばれ」のような表現をしてもいけない。
③トレーニングは本人ががコーチに相談して目標を設定して、自由に自分の判断で行う。
3.2.3 肺圧外傷防止
水慣れしていない初心者の講習、およびそれに引き続く訓練生の潜水で最もおそろしいのは、肺の圧外傷である。
近年、減圧症の防止については、充分に論議され治療施設も完備されて来ているので、減圧症による死亡事故の可能性は低くなっている。一方減圧症よりもおそろしい肺圧外傷については、あまり論じられなくなっている。
機序が単純であり防止方法も単純であるるからかもしれない。
スクーバから呼吸している状態から、呼吸をこらえ、息を止めて急浮上すると、あっけなく命を落としてしまう。肺圧外傷は、浮上による外の圧力の減少によって肺が過膨張して微細な肺胞と気管支が損傷を受け、肺が破れて起こる傷害であり、破れた肺胞から入り込んだ気泡により血管が塞栓されて起こる傷害であるから、空気塞栓(エアーエンボリズム)と呼ばれている。
もしもの場合には、分を争って再圧治療を開始するしか手立てがないが、かつては小型再圧タンクを設備していたダイビングリゾート、ダイビングサービスなどでも、現在では撤去してしまったところが多い。症例が少なく使用がまれ、もしくは使用が皆無であるのに整備しておく手間と費用がかかるからであろう。もはや治療の手段は実質的には無くなっている。その場に再圧タンクが無ければ、酸素吸入を行いながら、再圧タンクのある病院まで搬送する他にてだてはない。
一にも二にも予防を心がけるしかない。幸いなことにスクーバダイビングでも100本の経験を越えているようなダイバーは、水に慣れダイビングになれるから、肺が破損するまで呼吸を止めているようなことはなくなる。肺の圧外傷を防止する反射神経が形成されたと言うことである。
ここでは、潜水医学、高気圧障害については特別に述べないが、適切なテキストを読み充分にその徴候、症状、応急についての知識を得ておく必要がある。
※潜水士のテキストでも必要なことは記述されている。
肺圧外傷の可能性のあるトレーニングは禁止する。例えば、水中脱着は、1.5m以上の水深で行うことは禁止する。フリーアセントは、水平方向のタンク・エアーステーションに置き変える。コントロールアセントも望ましくない。バディブリージングの練習も水深1.5mを越える深さで行えば危険である。
なおスキンダイビングになれると、スキンダイビングは息をこらえて急浮上する習慣を付けてしまうので、スクーバの初心者がスキンダイビングの練習をすることには危険があるという考え方もあるがによって水に慣れれば、少しの注意で、息を止めて浮上するようなことは無くなる。
慌てて急浮上することが危険なのであり,常に慌てずにゆっくり浮上するようにすれば、スキンダイビングのエキスパートが息を止めて浮上するようなことはあり得ない。
また、これについては、スキンダイビングの練習に際して、水面近くで上を向いてスノーケルに息を吐き出して、スノーケル管の中の水を追い出しながら浮上するリプレースメントという方法に慣れることで、肺が膨張するに従って息を吐き出す反射神経が形成される。
要はスキンダイビングでもスクーバダイビングでも、肺に加わる水圧の変化と肺の中の圧力の変化に無意識に対応して肺圧と水圧のバランスを取る反射神経が出来ることで、肺圧外傷には、なりたくてもなれなくなる。
その段階に達するまでは、急浮上する可能性のあるスクーバダイビング練習項目を水深1.5m以上で行うことを厳禁する。
3.3 トレーニング参加基準
3.3.1 Cカードの所持
たとえば、ダイビングクラブを主催していて、C-カードを所持しているということで、無条件で活動グループに入れられるものだろうか。答えは否であることは、いくつかの事故が証明している。しかし、まずC-カードを所持している人に対して、トレーニングを開始する。
①指導団体の発行するCカードを所持していること。統括責任者、もしくはコーチが指導団体のインストラクターである場合には、エントリー・トレーニング終了後、その団体のCカードを発行できる。
②他の講習で発行されたCカードを所持していても、泳力確認基準、及びエントリー基準に到達していない場合には、エントリートレーニングを行う。
③エントリー・トレーニングは、コーチ及びそれに準ずるリード・ダイバーが、マンツーマンの形で直接安全管理で指導を行う。
3.3.2 健康状況報告書
①トレーニング参加時の報告書
所定の健康状況報告書を潜水前に提出するが、ダイビングは自己責任であるから、参加は本人の判断による。
しかし、健康状況について指導者に報告し説明することで相互に理解しておく必要がある。
虚偽の説明をしている場合も考えられるから、健康状況については一切の責任は本人以外に負いようがない。監督およびコーチは、健康状況の説明によっては参加中止を勧告することもあるが、一切の強制は行わないので、指導プログラムへの参加および不参加は、本人が決める。同時に事故発生については、一切の責任を追及しない同意書を提出する。
②トレーニング開始時の確認書
トレーニング開始前には、その都度簡略な確認書に健康状態を記入する。
持病のある場合、一年以内に入院、通院の治療を受けていた場合には、医師(できれば主治医)に相談する必要がある。健康状況について、医師の付記があれば、本人と相談し、持病による事故についての責任を家族に確認する。
持病がある場合には、相談の上、トレーニング内容を検討し、健康状況に応じて適切なものにするが、決してトレーニングを薦めてはいけない。
3.3.3 傷害保険(労災保険)の加入
①スポーツ安全保険
加入については、5人以上のグループを作らなければないので、統括責任者が一括して加入する。スポーツ安全保険は、トレーニングについてはカバーされるが、講習に類するものはカバーしないので、トレーニングと講習の区別を認識する。継続的に常時行うものはトレーニングである。
講習については、インストラクター賠償責任保険が適用される。
海での実習の際、活動分野の実習を兼ねて行ったならば、スポーツ安全保険ではカバーされない可能性がある。
②DANのオプション保険
活動ダイバー認定は、DANへの加入が義務づけられる。DANの加入とセットになっている保険は補償額が少ないが、国内でも国外でも事故の場合の救出費用などがカバーされ、ダイビングの安全について有益な機関誌の配布もある。
サイエンスの分野であれば、セットの保険ではカバーされないので、DANのオプション保険に加入する。
③普通傷害保険
サイエンス・ダイバーの場合、あるいは学生のクラブ活動では、学校が定める傷害保険(学生教育研究災害傷害保険など)に加入しなければならない。一般ダイバーであれば、統括責任者が適切な普通傷害保険、死亡保険金額が1000万円以上のものに加入しておくことが望ましい。
ここで、賠償責任に類する保険はスポーツ安全保険であるが、適用が不確かである。
考えられる全ての保険に加入していることで、事故の場合には、これらの保険の範囲内でだけ、補償が行われるものであることを、メンバー及び、メンバーの家族は了解、納得していることを証する同意書に署名捺印してもらう。
④労災保険
業務として潜水する場合には労災保険に加入するが、環境保全活動、研究活動の短期のアルバイト、あるいはグループのコーチなどの、労災保険加入については、今後の検討課題である。
労災保険は、雇用関係が成立し、事業者が労災保険に加入していなければ、保険は支払われない。
3.3.4 健康管理
①体調不良
40歳以上になれば、絶好の体調にあることはむしろ珍しい。60歳以上になれば、持病が二つぐらいあることは、当然になる。
スクーバダイビングは健康であれば、誰でも出来るということは、裏返せばどこかに故障があれば、ダイビングは出来ないことになってしまう。
ここでも自分の判断で決めなければならない。ダイビング事故の多くは健康状況に起因するものであり、これは、本人以外にはわかり得ない、あるいは本人でも予期していなかった健康上の理由で事故が起こる。他から見れば原因不明の事故になる。
防ぐ方法は、睡眠不足、飲酒、喫煙、など、意志によってコントロールできる不調の要因を避けることである。
健康診断は、潜水士の規則にあるように、六ヶ月毎に受けることが望ましいが、レジャーダイビングでも、少なくとも1年に1回の診断を受けて、自分の健康状態について把握しておくことが必要であるる。
自分の健康状況について、知覚し、自認していれば、不摂生を避け、トレーニングに励み、活動も無理をしなくなる。
②飲酒
飲酒がダイビングに悪い影響を及ぼすことはすでに周知であるが、飲酒をを止めることは難しい。
レジャーダイビングでは、飲酒も楽しみの一つと考えて、あくまでも自分の責任で適量を飲むことは、やむを得ないかも知れないが、飲酒した場合の事故については、過失責任を追及する資格はない。
ダイビング前夜に飲酒した場合には、ダイビング事故が発生して当然であることを免責同意書の項目に加えるぐらいが管理者として出来ることである。
飲酒がダイビング前夜に行われれば、事故、特に耳のスクィーズ、減圧症関係の事故が発生しても当然と考える。
統括責任者、コーチ、リードダイバーは、潜水前夜は絶対的な禁酒である。
③喫煙
喫煙について、健康に悪いことはすでに言い尽くされているが、スキンダイビングの息こらえ能力に、喫煙は目立って悪い影響を及ぼす。
3.3.5 家族への説明責任
水中活動に参加するダイバー本人は、自己責任の原則を充分に理解していて、リーダーや上級者を訴えることなどあり得ないと思っている。しかし、その家族、および周辺の人たちはちがう。
スクーバダイビング活動およびそのトレーニングに参加する者は、既に述べたのすべての保険に加入していても、深刻な事故の場合、家族および、周辺の人達は、責任者の賠償責任を追及する可能性がある。スクーバダイビング活動に参加する者は、水中での活動は、すべて自己責任であること、また、そのために厳しい基準とマニュアルを遵守するものであることを家族および周辺の人たちに充分に説明しておく。
リードダイバー、コーチ、統括責任者は、活動に先だって、参加メンバーに対して、スクーバ活動は講習会を除いて、賠償責任が無いことを認め、傷害保険以外には金銭的補償は得られないことを受忍する同意書に家族にもサインしてもらう。
各分野のリードダイバーおよびコーチは、賠償責任を問われる側であるが、統括責任者は、リードダイバーおよびコーチについても、その家族が一切の賠償責任を問わない同意書にサインしてもらう。
日本の訴訟の傾向として、このような免責同意書は、ほとんど効果がないという意見がある。もしそうであるならば、賠償責任保険が作れる講習、あるいは講習と見なされるツアー以外は、すべて、一人でソロで潜らせるより他に賠償責任に問われない方法はない。 ソロで潜ってもらうか、ソロダイバーどうしがバディを組む以外には、処置のしようがない。
バディが互いに責任を持つ、あるいは上級者が初心者を守るバディシステムを成立させるためには、基準とマニュアルが守られていることを条件として、訴えられた責任者は家族と対決する他ない。そのグループも協会も訴えられた責任者を守る。事故のあと、訴訟が起こるようなことがあれば、事故を起こした自分の名誉が保てないと、家族に充分に説明しておくる。
ただし、基準とマニュアルを守るという責任を果たさなかった場合には、統括責任者、コーチ、リーダーは、訴訟からも賠償責任からも逃れられないと知るべきである。
3.4 トレーニングの階層
3.4.1 プールトレーニング
プールもしくは、プール同等の水域でのトレーニング。
① エントリートレーニング
② 習熟トレーニング
③ 技能維持トレーニング
プールトレーニングでは、①②③いずれも、原則として同じプログラムをくり返すが、管理の体制がそれぞれ異なる。
①のエントリートレーニングは、必ずコーチもしくはリードダイバーがマンツーマンで行う。②③は、ユニットあるいはグループの練習会として行われるが、かならずバディで行う。浅いプールだからと言って、一人だけで、誰も見ていない状況で行ってはいけない。
3.4.2 泳力確認基準
スクーバダイビングは泳げなくてもできるが、アクシデントの場合の生存確率は、泳げなければ低くなる。分野にかかわらず、トレーニングを開始する際に各自の泳力を確認しておく。
泳力確認基準は1950年代からの古典的なものである。スクーバ活動をするダイバーは、どの国でも、この基準とほぼ同等の基準でチェックして、ダイビングを始めている。
なお、基準に満たなかったとしても、ダイビングを開始することはできるが、フィットネストレーニングを兼ねて、各項目を練習し、満たしておくことが望ましい。
フィン・マスク・スノーケルを使わない水泳であるから、どのプールでも行うことが出来る。
※40歳以上の場合には、全項目、フィン・マスク・スノーケルを着けて行っても良い。
※泳力確認は、安全管理を行うコーチの監視下で、チェックを受けながら行う。この場合にも強制してはいけない。もしも、基準に達しなければ、習熟トレーニングを行いつつ、泳力トレーニングも行い、機会を見て、一つずつチェックをしてもかまわない。
①フィン・マスク・スノーケルを着けずに、身体を水面に出さずに、20mを水平潜行できること。
②フィン・マスク・スノーケルを着けずに300mを12分以内に泳げる事 泳法は問わない。
③フィン・マスク・スノーケルを着けずに、10分間、もしくは手を使わないで2分間、立ち泳ぎができる事。
④フィン・マスク・スノーケルを着けずに、自分と同じ大きさの人を25m曳航できること。
⑤フィン・マスク・スノーケルを着けずに、水深3mからダイバーをレスキュー、引き上げられること。
3.4.3 達成維持基準
訓練生が活動ダイバー認定のために達成しなければならない基準であり、現役のダイバーで居る限り、生涯維持していなければならない水準でもある。
①活動ダイバーは、水深5m、水平距離25mのスキンダイビング能力を常時維持する。
②活動ダイバーは、フィン・マスク・スノーケルを使っての400m水面移動を10分以内で行えること。
③活動ダイバーは、完全なスクーバ水中脱着を3分以内にまとめられること。
活動ダイバーの認定証書には、2年ごとの更新であり、年間10回以上のダイビングを行っていない者は、達成維持基準の再評価と、訓練生と一緒の実海域潜水実習を少なくとも3回行わなければならない。
なお、年間10回の潜水は、一般に行われているレジャーダイビングへの参加でも良い。
3.4.4 実海域トレーニング
①基本実海域トレーニング
コーチが管理して、コーチもしくはリードダイバーが水中で直接管理を行い指導する。
②実海域実習
バディシステム遵守の上で、安全を第一の目標として行う。
③深度資格トレーニング
※ 深度資格は、20m資格、30m資格、40m資格であり、認定後に、その資格までの深度での活動が許される。20mまでの経験しか持たないダイバーが、40mに潜ってはいけない。20m、30m、40mと段階的なトレーニングを経て、40mまでの活動が許容される。
3.4.5 実海域トレーニング基準
①実海域トレーニングを開始するまでに、達成維持基準に到達していることが望ましいが、到達せずにプールトレーニング中途であっても、統括責任者、コーチの判断で、実海域トレーニングに参加させることができる。達成基準に達していない場合は、リードする先任のダイバーとバディを組み、コーチあるいは監督が水中で直接安全管理する体制で行う。
②活動ダイバー認定を受けているダイバーでも、年間で10回以上の潜水を記録していない場合には、実海域の技能維持トレーニングとして、少なくとも3回以上参加する。
③実海域トレーニングは、通常のダイビングと同様、無理をしないで、強制はせず、ダイビングを楽しむ。
レジャーダイビングのツアーダイビングをこれに含めてよい。
※トレーニングダイビングの途中で、マスククリアーをさせたり、バディブリージングをさせたり、BCをオーラルでふくらませたり、ましては、マスクをとりさったりしてはならない。これらの訓練は、プールもしくはプールと同等の状況で、その心構えをしてから行う。
④訓練生の活動ダイバー認定のための基本実海域トレーニングは、少なくともビーチエントリーを四回、ボートからのダイビングを二回行わなければならない。
⑤コンパスカードの読み方、ナイフの使い方などを実海域トレーニングの中途で行うが、その詳細はマニュアルで示す。
⑥活動ダイバー認定に際してプログラム通りの進行であれば、実海域での18回のダイビングで水準に到達するが、一般のツアーダイビングの回数で認定するならば、30回のダイビングで、認定できる水準に達するものとする。
基本実海域トレーニング、深度資格が認定の水準に達し、泳力確認基準と達成維持基準の目標に相当する能力があると認められた後、統括責任者とコーチが総合的に判断して、活動ダイバーとして認定することができる。
3.5 深度資格と認定
3.5.1 深度資格と認定条件
①20m深度:スポーツ・エキスペディション認定条件
②30m深度:サイエンスダイバーの認定条件
③40m資格:リードダイバー認定条件
※各深度の潜水で、コーチが判断して問題があれば先に進んではいけない。
性急に先に進もうとしては危険である。
深度資格の基準は新たにトレーニングを開始したメンバーについてのものであり、すでにスクーバダイビングを相当回数経験している人の場合には、そのログブックと基準とを見比べて、適切な判定を行い、資格を定めることができる。
深度資格は、認定ではないので、各統括責任者は、随時適切なカード、あるいは証明を作って達成したメンバーに渡すことができる。
3.5.2 水深10m資格
①参加資格
ビーチエントリーを四回、ボートからのダイビングを二回の基本実海域トレーニングを修了していること
②トレーニング内容
水深10m以内の潜水を4回経験する。
(二日間 4本)
実海域基本トレーニングからの潜水回数は、10回になる。波高50cを一回、透視度2m以下の体験を基本実海域トレーニングで終了していなければ、ここで体験する。
③スキンダイビング達成維持基準をクリアーしていなければ、20m資格に進んではいけない。
3.5.3 水深20m資格
①参加資格
水深10m資格を持っていること
②トレーニング内容
水深10m~20mの潜水を4回経験する。積算潜水回数は14になる
20m資格は、スポーツ・エキスペディションの認定の条件の一つである。
スポーツ・エキスペディション認定
①水深20m資格を達成し、実海域での積算潜水回数14
プールトレーニングで達成維持基準に達していること
②統括責任者の指定する学科テストスクリーニングを受けていること。
潜水士国家試験の受験が望ましい。(サイエンスでは必須)
③統括責任者とコーチが、グループ内の潜水を評価して、認定する。
④プールトレーニングで達成維持基準に達しており、積算潜水回数30回以上で、一般指導団体の中級に相当する認定を受けていれば、統括責任者とコーチがグループ内の潜水を評価して認定できる。
3.5.4 水深30m資格
①参加資格:水深20m資格を持っていること
②水深20m~30mの潜水を4回経験する。積算潜水回数は18回になる。
③サイエンスダイバーの基本資格認定の条件の一つである。
サイエンスダイバー認定
①水深30m資格を達成し、実海域での積算潜水回数18回
プールトレーニングで、達成維持基準に達していること
②統括責任者の指定する学科テストスクリーニングを受けていること。
潜水士国家試験に合格していること
③統括責任者とコーチが、グループ内での潜水を評価して認定する。
3.5.5 水深40m資格
①参加資格
水深30m資格を持っていること
②内容
水深30m~40mの潜水を4回経験する。
③リードダイバーの条件である。
3.6 レスキュートレーニング
3.6.1.救急蘇生法
日赤、消防庁などが行う救急蘇生法トレーニングに参加する。
救急蘇生法は手技であるから、なるべく多く体験し、いつでもどこでも行えるようにしておく。
各グループなどでも、救急蘇生法の訓練を受けている、例えば酸素プロバイダー、インストラクターなどを指導者として、なるべく数多く練習会を開催する。
3.6.2 泳力トレーニング
すでに述べた泳力確認基準、達成維持基準を確定している上で、意識がある事故者を曳航する(もしくは押す)練習を体験する。
ハードな曳航はする必要がない。どの程度の泳力が必要であり、どの程度消耗するかを体験すれば良い。
ハードなレスキュートレーニングで死亡事故が発生したこともある。